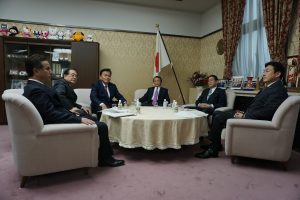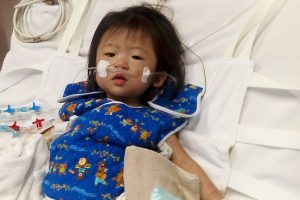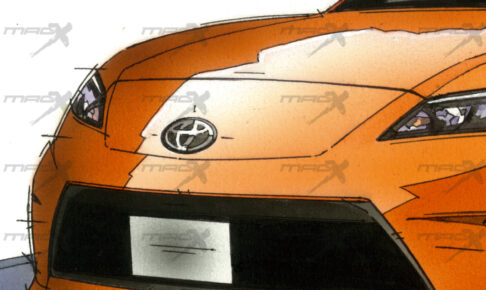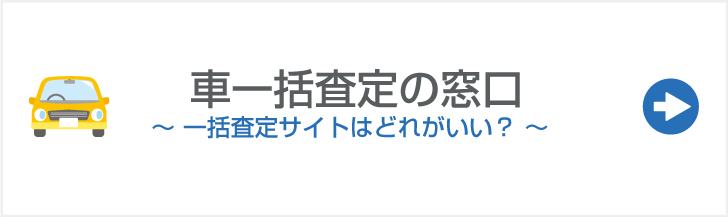マレーシアの人口は約3350万人で、タイの約半分、インドネシアの約8分の1だが、新車販売台数ではタイを抜いて1位インドネシア、そして2位がマレーシア、3位タイとなっている。
自国ブランド(プロトン、プロドゥア)を持つのが最大の特徴で、首都クアラルンプールでは、国民車とも呼ばれる両ブランドのモデルが溢れている(プロトンは中国ジーリー傘下で多くはジーリーモデルがベース、プロドゥアは出資しているダイハツ系モデルがベースとなっている)。

世界的にクロスオーバーSUVの人気が高くて販売の中心となっているが、クアラルンプールではセダンやハッチバックもまだまだ存在感を放っており、これもタイやインドネシアとは異なる傾向と言えるだろう。
6年ぶりの開催で「クアラルンプール国際モーターショー」から「クアラルンプール国際モビリティショー(KLMS)」に改名されたKLMSの一般公開日初日(12月5日)に会場内を歩くと、タイやインドネシアの自動車ショーにはない違和感を覚えた。
タイやインドネシアの自動車ショーでは一般公開日になると、各ブランドブースともにかなり多くのセールスマンが配置され、来場者への積極的な売り込みが行われる。両国は自動車生産拠点を持つものの、自国ブランドが存在しないこともあり、会場で新車を販売するトレードショーに完全に特化している。腕利きのセールスマンを会場に配置し、そのセールスマンが抱える販売見込み客へ自動車ショーの無料招待券を渡して誘致することで主催者としても来場者数の確保ができるというわけだ。
また、タイでは会期中の新車販売台数も発表され、主催者としてはこれを重視しているようだ。会期中の新車販売台数を稼ぐために店頭での契約を待ってもらい、会場で正式契約に持ち込むこともあると聞く。もちろん会期中に会場内で契約した購入者には契約特典も用意されている。
話をKLMSに戻すと、まったく販売活動が行われていないわけではないが、ブース内がセールスマンで溢れかえっているということもない。タイやインドネシアでは多くのブランドで広大な商談コーナーを設けてファイナンス会社がローン審査のために出張カウンター(東南アジア各国ではローンで購入するのが原則のため)を用意して万全の体制で臨むが、KLMSではテーブルは用意されているものの「商談コーナー」と呼べるようなものではなかった。
一般公開日初日は朝から午後3時ごろまで会場にいたのだが、来場者は思っていたほど多くはなかった。出展する完成車ブランドが少なめで、しかも人寄せパンダ効果抜群のメルセデスベンツやBMW、レクサスなどがブースを構えず、会場自体もコンパクトなので「回転が良い(短時間で来場者が帰る)」こともあるのだろう。タイやインドネシアのように新車ディーラーが無料招待券で購入見込み客を積極的に呼び込むことなく、入場料金を払って見にいこうという人がメインともなれば、来場者の勢いもこんなものなのかもしれない。


KLMSは2023年に日本で開催されたジャパン・モビリティ・ショー(JMS)を参考にしたとされるが、JMSを成功に導いたひとつの要因でもあるエンタテインメント的要素を強く感じることができなかったので、今後のKLMSを盛り上げていくためには、エンタテインメント的要素をいかに付加していくかにかかっていると言えよう。