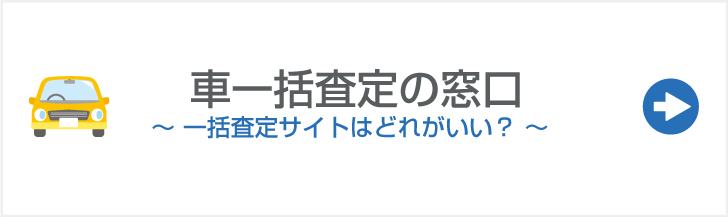マツダが機能強化の一環として東京本社を麻布台ヒルズに移転し、併せて「R&Dセンター東京(略称:MRT)」を開設した。東京本社が移転するのは約5年半ぶりで、これまでの霞が関ビルを後にした。


新拠点は麻布台ヒルズ森JPタワーの49階に入居している。
 自らをスモールプレーヤーと呼ぶマツダはこれまで開発・生産・マーケティングなどを地元・広島に集約して効率よく業務を行ってきた。しかし、近年はクルマの電動化と知能化が急速に進んでいてソフトウェア領域の開発機能強化が欠かせない。
自らをスモールプレーヤーと呼ぶマツダはこれまで開発・生産・マーケティングなどを地元・広島に集約して効率よく業務を行ってきた。しかし、近年はクルマの電動化と知能化が急速に進んでいてソフトウェア領域の開発機能強化が欠かせない。
執行役員で広報・渉外などを担当している滝村典之さんは「広島一極集中に捉われず、首都圏機能の強化を進めている」「ソフトウェア開発の人材確保が喫緊の課題で、魅力的な(執務の)拠点が必要だった。人材が集まっている首都圏に積極的に参入する」と狙いを説明した。つまりは、首都圏のほうが人材を確保しやすいといったホンネが見え隠れする。
「首都圏には多くの大学が存在していて新卒者の数も圧倒的に多い。また、キャリア採用においても東京は人材が多いので、採用機能は東京に集約したい」との意図も聞かれた。実際に好影響が現れていて「1年前に東京本社の移転とMRT開設を発表した後は応募者数が増えており、意図した結果が出ている」とした上で「もっとも効果的な発信源は口コミなので、エンジニアのコミュニティで浸透すれば」と期待を寄せる。
同じく執行役員で統合制御システム開発を担当している今田道宏さんは「ソフトウェア開発拠点を設置することで、1)採用、2)共創、3)連携、の3点を推し進めたい」とした。このMRTにはコネクティッド・ソフトウェア開発グループと、先進安全技術開発グループが置かれる。

新設されたR&Dセンター東京。
「海外ではなく、国内に新拠点を開設した意図や狙いは?」との質問に対して今田さんは「拠点は分散しすぎないほうがいい」と答え、滝村さんも「ソフトウェアに依存する部分は増えているが、ハードウェアがなくなるわけではない。両方の拠点を遠くしすぎるのはよくない」として国内で開発体制を強化していく考えを示した。
首都圏機能の強化策としてマツダは24年2月、東京・六本木にイノベーションスペース東京を、今年2月には同じく都内の南青山にブランド体感施設を開設した。
六本木にあるイノベーションスペースとの違いが気になるところだが、「六本木は予測できない化学反応に期待した出会いのスペース。MRTは道筋が見えている開発を手がけ、さまざまなスキルを持った人材が集まって共創する拠点」(滝村さん)だという。
参考までに、南青山に誕生したMAZDA TRANS AOYAMAの月間平均来場者数は1万人を維持しており、うち半数はマツダ車を購入したことのない消費者で、新たな接点の場として機能している。

東京本社には席が自由に選べるフリーアドレス制が取り入れられている。

6つの応接室が用意されている。

外部からの来客の応対場所も兼ねる「共創」スペース。


ソファー席からは東京タワーが見える。